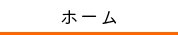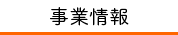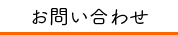Home >理事長所信
理事長所信
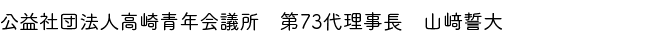

スローガン
NEXT STAGE
~持続可能な社会の幕開け~
基本理念
次の世代に対し責任を持ち、笑顔が溢れる持続可能な社会をつなぐ。
基本方針
- 1.JAYCEEよ、地域づくりの旗手となれ
- 2.「まち」と「地域資源」を繋ぐ共生社会の創造
- 3.自然を思う次の世代の主役、地球市民の創造
- 4.固有の文化を継承しまちを明るく・美しく
- 5.自信と誇りを持って力強く活動するJAYCEEの発信
- 6.青年経済人としての品格
- 7.継承と進化、時代に即した組織運営
所 信
【はじめに】
今から73年前、戦後間もない1951年9月1日に高崎青年会議所が誕生しました。戦後の荒廃から日本経済や地域社会を立て直そうと強い信念を持って運動された先輩諸兄姉のご尽力の末に、高崎のまちづくりの礎が築かれました。その礎は、次の世代へと引き継がれ、変わりゆく社会課題に真摯に向き合い、長きにわたって力を注いでこられた先輩諸兄姉の志によって、高崎は見事に「明るい豊かな社会」へと変貌を遂げました。
1985年、世間はバブル景気に沸き、ゆとりがあり、安全で量感のある豊かな社会基盤の上に、私は誕生しました。私たち、青年会議所が掲げるビジョン、「明るい豊かな社会の実現」は、私が生まれた時代には、その示す姿は定かではないですが、ある程度、達成していたように思えます。
豊かな時代に生まれ育った私には、「明るい豊かな社会の実現」という青年会議所のビジョンが、漠然とした抽象的な概念に留まっているように思え、現代の高崎青年会議所を担う私たちの運動の目的は「何であるのか」を考えるようになりました。
「明るい豊かな社会」が築かれた今、私たち現役世代は、何を目標とし、どのような運動を展開すべきなのでしょうか。このような疑問を持ちながらJC運動を続けていた時、公園で遊ぶ子どもたちを見ていてふと頭に浮かんだことがあります。「この子たちの笑顔は持続可能なのか」。
私は今、高崎青年会議所は次のステージに上がり運動を展開する転換期に差し掛かっているのではないかと考えます。次のステージとは何でしょうか。私は、先輩諸兄姉が築き上げた、この豊かな社会を持続可能な形に変えていくことが、私たち現役世代に託された役割であり、運動の目的ではないのかと考えます。
なぜそのように思えるのでしょうか。正直申し上げ、私は今の豊かな社会が持続できる状態にあるとは到底思えないからです。
地球温暖化や局地的な暴風雨などの異常気象、土砂崩れや川の氾濫、生物多様性の崩壊、大気・水・土壌の汚染などの環境問題、世界的な人口が急激に増加することによる貧困や食糧危機の問題があります。これらの問題を引き起こしているのは、紛れもなく現代を生きる私たちであり、未来に生きる人に対し、マイナスの影響を及ぼすことは疑う余地はありません。私たちは、先人から贈られた豊かな社会を、些か好き勝手に使い過ぎてしまったのではないでしょうか。
私は、自分の子どもや、孫にも、私たちが生きた豊かな社会を残してあげたいのです。私たちはこのまちに住む高崎市民であり、地球の恩恵を受けて地球上に暮らす地球市民です。かけがえのない地球を"ふるさと"と呼べる"こころ"を持った地球市民が一人でも多く増えれば、このまち、この地球は、もっと美しく、そして持続可能になれるのではないでしょうか。
幸いにも、このまちには、豊かな暮らしを続けられる機能が備わっています。それは、居住機能や医療・福祉・子育て・商業等の「都市機能」であり、文化や歴史的資産、清らかな大気や水、それらが育む農畜産物を作り出す健全な「生態系機能」です。高崎は、「都市」と「生態系」の二つの機能を持った唯一無二の都市です。この二つの機能を壊すことなく、お互いが影響を与えながら共存共栄するまちは、その魅力に惹かれ人々が集まり、豊かな暮らしを次の世代へと引き継ぐことができます。
さぁ、はじめましょう。誇り高きJAYCEEとしての意識、共通の目的を持って果敢に挑戦する仲間としての認識、そしてこの時代に生き運動を展開する意義を自覚し、笑顔が溢れる持続可能な高崎を次の世代へとつないでいきましょう。
【指導力 ~JAYCEE よ、地域づくりの旗手となれ~ 】
新しい価値観を持って持続可能な社会を創造していくのは、一人ひとりの人間にほかなりません。
まちを創るのも人、歴史を創るのも人です。私たちJAYCEEは、市民社会の中にあり、市民の先頭に立って、明るい豊かな明日のために働きかける人格を持った人間でなくてはなりません。青年会議所は、「青年が社会により良い変化をもたらすための発展と成長の機会を提供する」ことを使命とし、民主的な集団指導力、あるいは集団運営能力の研究と実践の機会を提供してくれます。
私たちは、一人の青年経済人として、会社の成長はもちろんのこと、家族を守り、子どもを育て、日々大きな重圧と責任を背負い、限られた時間の中で高崎青年会議所に入会し活動しています。私たちは、暇ではありません。だからこそ、青年会議所の活動を通じて、自ら厳しく訓練し、指導者たる誇りを持ち、まちのため、家族のため、会社で働く社員のために自己成長に励み、その成果を、みんなの希望に変えていく必要があります。
私たちは今、人口減少や少子高齢化による生産人口の減少、静かに迫りくるデジタル経済での競争など、経営環境は目まぐるしく変化し、先が見えない状況に置かれています。このような状況で私たちが生き抜いていくためには、未来を推し量る「想像力」と、未来を見据えた「創造力」が求められると考えます。様々な領域の情報にアンテナをはり、多様な価値観に触れ、仮説を立てる習慣を身につけることが必要であり、創造には、集団である組織をまとめ効率的かつ円滑に運営し、メンバー一人ひとりのパフォーマンスを最大限に引き出す能力が求められます。
「想像力」と「創造力」を養うことは、まちづくり運動を牽引する原動力となります。「持続可能な社会をつくる」高い志と能力を兼ね備えた地域づくりの騎手になりましょう。
【経済 ~まちと地域資源を繋ぐ共生社会の創造~】
このまちは「地域資源」で溢れ、「地域資源」を消費する「まち」が存在します。
桑の葉を栽培し、蚕を育て絹織物の原料となる糸を生産し、それを「まち」で売る。高崎の歴史的な背景からも「地域資源」と「まち」の連携によって、産業と地域がバランスよく発展してきたことが理解できます。そして、1884年5月、高崎の経済発展を後押しするかのように高崎線が開通しました。まさに、産業と交通が結びつき、高崎が交通の要衝として動き始めた原点であります。現在では、高崎市の商業売上は中核市で1位を誇り、群馬県の玄関口である高崎駅には商業施設やオフィス、ホテル、高崎アリーナや高崎芸術劇場などが建ち並び、毎日多くの人々で賑わい、青年会議所のビジョンである「明るい豊かな社会」を象徴しています。
他方、健全な生態系機能を有し「地域資源」を生み出す里山はどうでしょうか。人口減少や高齢化により、耕作放棄地や森林の荒廃が広がっています。高崎は今、「地域資源」を失いかけています。
「まち」には、資金や人的資源があり、里山には、食料や水、木材などの豊かな「地域資源」があります。「まち」と「地域資源」の共生には、経済的な繋がりを構築していくことで、共存共栄するバリューチェーンを生み出し、お互いが影響を与えながら支え合う、そのような姿が、このまちのあるべき姿であり、そこに、持続性を持った都市をつくる要素があるように思えます。唯一無二の魅力を持った高崎の強みを生かしたエコシステムの構築は、高崎をより強く、自立分散型の都市として確立できるでしょう。
【教育 ~自然を思う次の世代の主役、地球市民の創造~ 】
自然や生物からの恵みのうえに、私たちの暮らしは成り立っています。しかし、私たち人間は、自分たちの生活水準の向上のため、また新しいものを作り出したいという好奇心や願望のために、自然を壊して何か新しいものを作ろうとします。これにより、自然や生物たちの繋がりが脅かされ、絶滅の危機にさらされている生物が増えているのが現状です。私たちは、豊かさや便利さに関心を寄せ、自然や生物には無関心なように思えます。
私は、就職を理由に住まいを東京に移しました。自然や生き物との距離は遠ざかり、ビルの林立するコンクリートジャングルでの生活です。当時を思い返せば、自然や生き物に意識を向けることは、殆どありませんでした。
私が小学生の頃の高崎には、自然が残り豊かな生態系が息づいていました。会社の周辺に広がる田んぼには、オタマジャクシやカエルが生息し、秋の夜には虫の声が綺麗に鳴り響いていました。実家近くの親水公園には、タニシが生息し、蛍が夏の夜を明るく彩っていました。今はどうでしょうか。田んぼの上に住宅が建ち、蛍は見ることができなくなりました。昔と比べ、今の子どもたちは、自然や生き物との距離が離れつつあります。
子どもの頃から自然とふれあう機会を多く持たせ、子どもの美しい感受性や五感を刺激することが不可欠です。子どもたちの世界は、いつも生き生きとして新鮮で美しく、驚きと感激に満ち溢れています。残念なことに、私たちの多くは大人になるまえに澄み切った洞察力や、美しいもの、畏敬すべきものへの直観力を鈍らせ、ある時は、まったく失ってしまいます。
子どもから大人まで豊かな恵みを享受する自然とのふれあいは、「自然への感受性」や「自然の変化に気づき、共感する力」を育み、生態系の一部である人間が、自然と共生する大切さを理解することに繋がります。このまちには、自然という教材が身近に存在しています。かけがえのない地球を"ふるさと"と呼べる"こころ"を持った地球市民を育んでいきましょう。
【文化 ~固有の文化を継承しまちを明るく・美しく~】
高崎の音楽文化を表現する言葉に「音楽のある街・高崎」があります。
親に連れられて参加した「森とオーケストラ」や「マーチングフェスティバル」では、幼少期から音楽に触れ、今でも高崎駅周辺では音楽が鳴り響き、高崎はあらゆるところで音楽と触れることの多いまちです。
高崎青年会議所創立25周年記念公演として開催された「21万人市民と群響による手創りの音楽会」や「群馬音楽センター」の建設では、市民を巻き込んだ音楽文化の創造に、当時の先輩諸兄姉の血のにじむ努力と強い志を感じることができます。市民に音楽文化を伝え、地域愛を育む「森とオーケストラ」は、昔と変わらず今も多くの方を惹きつける運動として、今年で46回目を迎えます。
文化は、他者に共感を生み、人と人とを結び付け、相互に理解し、尊重し合う土壌を提供するものであり、人間が協働し、共生する社会の基盤をつくる力があります。
高崎の音楽文化は、まさにこれらの目的を体現し主張するものであり、この文化を牽引されたのが先輩諸兄姉であったことに、心より誇らしく思います。
今、高崎は都市化が進んでいます。激しく移りゆく時代の中で、消えゆく郷土の文化や歴史を守り、次の世代に伝えていくことを私たちは、忘れてはなりません。高崎には、音楽以外にも、美しい文化が存在します。日本の原風景を感じさせる里山には、伝統的な田舎生活と自然が融合した美しい景観が広がります。自然と共生し、長い年月をかけて培われた里山は、ただ美しいだけでなく、田舎の伝統的な暮らしや文化が息づいています。私たちの愛する故郷には、そのような美しい里山が存在し、すぐに会いにいくことができます。生物多様性があるからこそ、さまざまな文化や自然にかかわる活動が生まれています。
例えば、農村で行われる収穫祭や自然の恵みに感謝するお祭りがありますが、それぞれの地域で生物多様性との繋がりから、独特の伝統文化が育まれてきました。
自然が豊かで穏やかな時間が流れる里山は、次の世代に残していくべき高崎の重要な資産の一つです。季節ごとの祭りや儀式、伝統的な郷土料理や農法、そして工芸など、里山に息づく固有の文化を見つけ、市街地に住む住民に伝え、興味・関心を持ってもらいましょう。文化を通じた里山と人間の共生は、高崎を明るい豊かな社会へと導いていくでしょう。
【広報 ~自信と誇りを持って力強く運動するJAYCEEの発信~ 】
「JCの役割は終わった」、「JCは飲んで騒いでいる」、「JCは二代目、三代目のボンボンのたまり場」、まちではこんな声をよく耳にします。私は、その声を聞くたびに強い憤りを感じます。
私たち高崎青年会議所は、創設から今日に至るまでの73年間、誰よりも、どの団体よりも、愛してやまない高崎のことを考え、課題を見つけては、誰よりも先に動き出してきました。これは紛れもない事実であり、私たちのプライドと誇りの源泉になっています。現役世代である私たちも、連日連夜、喧々諤々と議論を重ね、高崎を明るい豊かなまちにするための一筋の希望を見出そうと努力を重ねています。
そんな、地域の未来のため、自分自身の成長のため、自信と誇りを持って力強く運動する、私たちJAYCEEの姿勢をより広く、そして正しく発信し、認知・共感してもらうことが「一緒に活動したい」と思う仲間を増やし、「JCが、このまちにあってよかった」と思う地域の方々からの信頼を得られることに繋がります。
「明るい豊かな社会を築く」この大きな使命を成し遂げるには、多くのメンバーの英知と勇気と情熱を結集させ、失敗を恐れず果敢に挑戦し続ける組織であり、なによりも地域住民の協力なくしてはなし得ません。そのような組織をつくるには、私たちの活動に共感してもらえる仲間を増やすことが肝要です。そのためには、SNSを通じた情報発信や、地域住民や行政関係者など、まちづくりのステークホルダーとの良好な関係を構築し、また広報活動の効果を検証し次に活かすことも重要になります。自信と誇りを持って力強く運動する、私たちJAYCEEの姿勢を発信していきましょう。
【会員 ~青年経済人としての品格~ 】
私たちは、明るい豊かな社会の実現に向けた運動を、持続的に行う必要があります。そのためには、メンバー一人ひとりが青年会議所の魅力を理解し、それを伝えていくことが重要になります。私たちは高崎のまちづくりを先導する旗手であり、次の世代の地域経済を担う若手経営者・後継者・経営幹部です。企業の発展と地域社会の形成は、私たちに課せられた使命であることを自覚する必要があります。
青年会議所は、私たちに「発展」と「成長」の機会を提供してくれます。そのためには、JC運動にただ参加するのではなく、「自発的」に参加する意識を持つ必要があります。自発的とは、「JCとは自分にとってどのような場所か」、「自分はJCにおいて何をなすべきか」を真剣に考え、明確な目的意識を持って参加することです。「仲間が欲しい」、「仕事が欲しい」、「まちづくりがしたい」、「自己成長したい」、「なんだかよくわかってないけど、誘われたから入会した」など、入会動機は人それぞれです。しかし、JCメンバーである以上、自分や仲間の成長のため、愛する故郷のため、明確な目的と使命を持って何事にも真摯に取り組む姿勢が重要になります。目的意識を持つことができるかどうかで、JCに入った効果に圧倒的な差が生まれます。
目的意識を常に持ち、まちに対する強い愛着を持ち、自分のため仲間のために誰よりも努力を重ね、凛然たる佇まいで、魅力ある青年経済人になりましょう。
【組織 ~継承と進化、時代に即した組織運営~ 】
青年会議所には、「奉仕・修練・友情」という三信条があります。これは私たちのJC活動の根幹を示す信条であり、この三信条を会得していくことが、青年会議所に在籍する一つの目的です。三信条を創り出すのは集団であり「組織」です。組織を統制し、メンバー一人ひとりが、最大のパフォーマンスを発揮するためには「統一した決まり」が必要です。高崎青年会議所には、定款や各種規程が存在します。個人の勝手な考えや行動が組織の力を弱体化させます。皆でルールを守って円滑な組織運営を心がけましょう。
そして、近年、私たちが頭を悩ませているのが、「会員の減少」です。 会員減少は歯止めがきかず、全LOMの統計からも年々減少に転じていることがわかります。
会員の減少は、予算面において、あらかじめ決められた範囲内での活動や、これまで出来た規模の事業を縮小して行うことを余儀なくされます。そのような状態で、本質を捉えた社会開発や指導力開発ができるのでしょうか。そのような高崎青年会議所で良いのでしょうか。疑問を抱いています。皆さんから預かった大切な活動資金をどのように使うかは、私たちの自由な判断であり、第三者に縛られるものではないのです。会費の使途は、その年、その環境に即した活きたお金にしなければなりません。大切な活動資金は、社会開発、そして私たち自身を高める事業や、会員同士の絆をより深める事業に生かすべきではないでしょうか。
私たちも持続可能な団体でなければなりません。将来の明るい高崎青年会議所を想像して、私たちはどうあるべきかについて、今一度考えていきましょう。
【結びに】
私には大切にしている言葉があります。それは、「地球は先祖から譲り受けたものではない、子孫から借りているものだ」です。人に物を貸して、それが汚れ、修復ができないくらいに壊されて返ってきたら、あなたはどのように思いますか。私たちはきれいな川が好きです。私たちは緑豊かな山が好きです。そして明るい豊かな高崎が好きです。未来に生きる人たちもきっと同じはずです。
笑顔が溢れる持続可能なまちをつくるのは、現代を生きる私たちです。
私たち高崎青年会議所は、次のステージに立っています。この豊かなまちを、次の世代のために持続可能な形に変えていきましょう。「つくる時代」から「つなぐ時代」へ、私たちの役割は次のステージへと移行します。「NEXT STAGE」、若き青年の英知と勇気と情熱を結集して、持続可能な社会づくりの幕を開けましょう。